「寝ても寝ても眠いんだよね。貧血と関係ある?」
先日、友人とそんな話になりました。
最近はテレワークで家で仕事をすることが多く寝る時間も今までより少し多めに確保できているのだとか。
しかしなんでもかんでも貧血のせいにしてません?
でも「寝ても眠いことと貧血」か〜

そこで今日は
寝ても寝ても眠いことと貧血は関係あるのか?
について考えてみたいと思います。
今回も医学論文を掘りまくってみました。
いつものように2行でまとめていますのでぜひ参考にしてください。
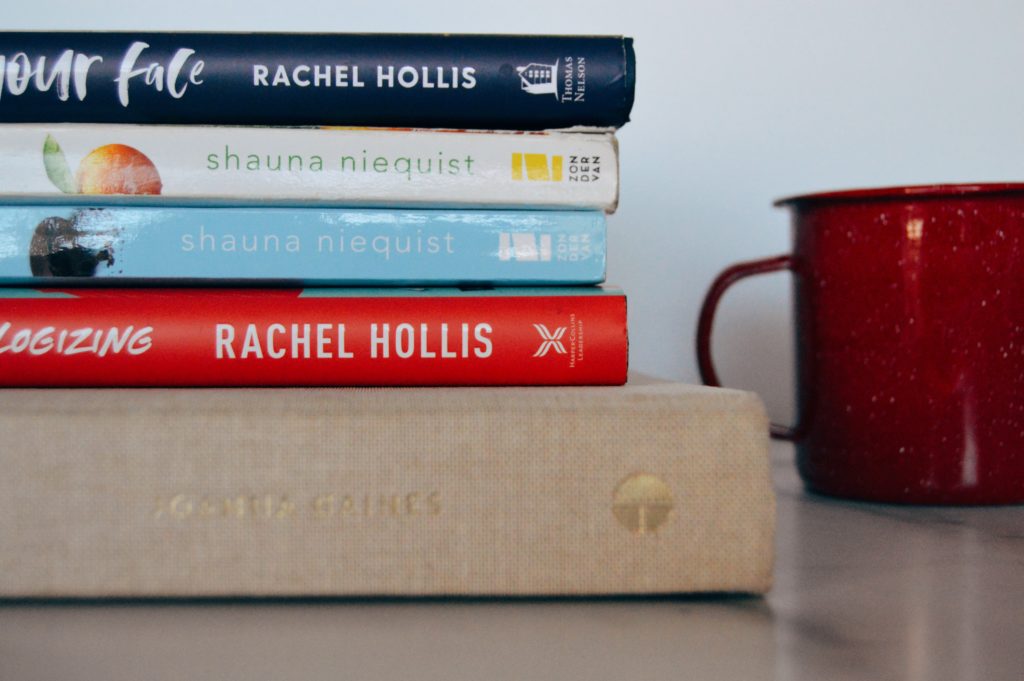
どうして人は眠くなるの?
これにはいくつか理由があります。
代表的な例を挙げますね。
①脳を休ませるため
睡眠をとらないと脳が休めず適切に働かなくなります。
②交感神経を休ませるため
自律神経は交感神経と副交感神経の2つから成り立っています。
人間の意思とは関係なく働く神経のことで心臓を動かしたり体温のコントロールなどをしてくれています。
サンナナサロン的に自律神経とは「ONOFFのスイッチで元気のバロメータ」と考えています。
睡眠をとらないと自律神経が上手く働かなくなり不必要な時にドキドキしたり発汗するなどカラダに不調が見られることになります。
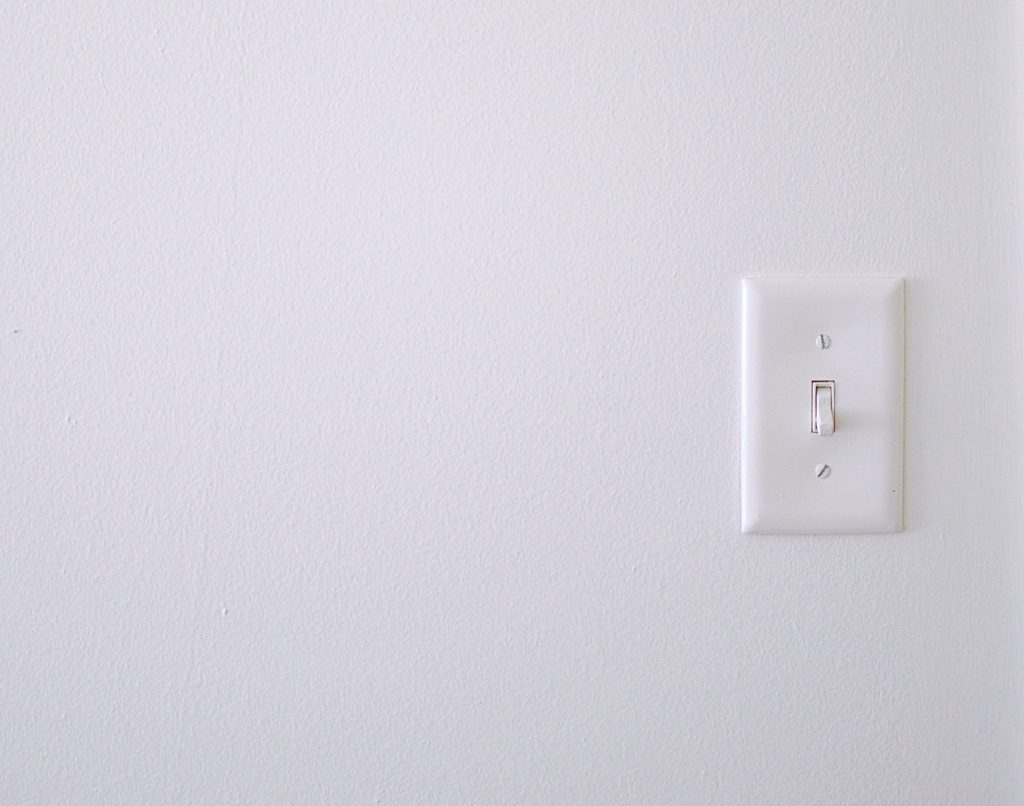
③体を回復、成長させる
人が睡眠する際には成長ホルモンが分泌されています。
この成長ホルモンが細胞の修復や筋肉などの成長に関係しているため睡眠が必要となります。
眠ることは人が生きていくために必要なのですね。
【参考ブログ(信憑度:B+)】
『なぜ人間には睡眠が必要?人間が獲得した睡眠の性質5つ』
(weara blog編集部/2020年)
<記事のまとめ>
・睡眠とは食料が確保できない時間帯にエネルギーをできるだけ使わない状態を維持するために進化の途上で獲得した生命現象である。
・特に人間は脳を特異的に発達させてきた過程で独特な睡眠の性質を獲得したと言われている。

では本題。
寝ても寝ても眠いことと貧血は関係あるのでしょうか?
カラダが貧血を何とかして欲しいと訴えているのか?

結論はズバリ
●寝ても寝ても眠いことの原因の一つとして貧血が挙げられる
●眠たくなるのはカラダの酸素が不足しているため
です。
少し説明しますね。
貧血によって引き起こされる「寝ても寝ても眠い」はカラダに必要な酸素が足りないことが原因です。

まず貧血について説明しますね。
人間は何十兆個の細胞から出来ておりそれらの全ての細胞が酸素を使って生きています。
この細胞に酸素を運ぶのは血液中のヘモグロビンのお仕事です。
ヘモグロビンは酸素を運ぶカートの役割をしておりヘモグロビンが足りなくなるとカラダ中の細胞に十分な酸素が運べなくなります。
これが貧血です。

カラダの酸素が足りなくなったら何が起こるのでしょうか?
実は脳が酸素を使う量を減らそうとします。
眠ってしまえば少ない酸素ですむため脳はわざと眠くして酸素をなるべく使わないようにするのです。
●カラダの酸素が足りなくなる
↓
●自律神経が脳で使う酸素を減らそうとする
↓
●脳がわざと眠たくして酸素を使わないようにする
【参考ブログ(信憑度:B+)】
『昼食後に襲ってくる強烈な眠気。原因は鉄分不足かも?』
(心療内科本郷赤門前クリニック院長吉田たかよし先生/2020年)
<記事のまとめ>
・十分に睡眠を取っているにも関わらず昼食後に眠くなることについて貧血の観点から解説。
・貧血で鉄分が不足しカラダの酸素が足りなくなった場合は脳がわざと眠くすることで酸素を使う量を減らす。
実際に寝ても眠いと訴える患者に対しヘモグロビンの材料である鉄とビタミンB12を摂らせることで症状が良くなった例もあります。
【参考文献(信憑度:A-)】
『鉄欠乏性貧血治療後に必要な食事対策』
(鹿児島市医報 デイジークリニック武元良整先生/2017年)
<記事のまとめ>
・寝ても寝ても眠いと感じる倦怠感が主訴の40代女性の症例について報告。
・最終診断は潜在性鉄欠乏症とビタミンB12欠乏症。

まとめ
今回は寝ても眠いことと貧血の関係についてお話ししました。
寝ても眠いと感じることの原因の一つとして貧血が挙げられます。
貧血によってカラダの酸素が足りなくなると自律神経の働きで脳で使う酸素の量を減らすため眠くなってしまいます。
仕事に影響が出たり物事を深く考えたくても出来なくなってしまいます。
貧血を治すことで健康的なカラダ作りを心がけましょう!
今日からできる正しい知識を2つ!まとめます。
●十分な睡眠を取りましょう。
(人間のカラダの回復に睡眠は必要です)
●栄養素のバランスの良い食事を摂りましょう。
(普段からの栄養摂取が大事です)
正しい知識で貧血を撲滅しましょう!





